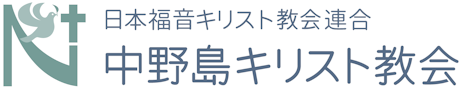コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2025年8月24日 主日礼拝
序
- イスラエルが南北に分裂していた時代に、主は正しい信仰から逸脱した北王国において、偉大な預言者を起こして、頼るべき真の神はご自分であることを示された。
- 最も代表的な預言者はエリヤ。バアルの預言者たちと、どちらの神が奇跡を起こせるかという対決をし勝利したことが有名。エリヤの後継者がエリシャ。彼も数多くの奇跡を行い、主の偉大さを示した。それらの奇跡の目的は頼るべきお方が誰であるのかを示すことだった。
1.
- イスラエルの隣国アラムは、エリシャの時代、しばしばイスラエルと交戦する敵対関係にあった。しかし主はアラムにも恵み深く、ナアマンという軍の長によって勝利も与えられた。主は正しい信仰を持つ人にしか恵みを与えないのではなく、すべての存在に対して恵み深い。この点を見失うと、信仰が神の恵みを引き出すための「取引」や「呪文」になってしまう。人間本意になることを主は望まれない。
- 主は偉大な方であり、人に操られることはない。人がどんなに捧げても、物を必要とはしていない。崇拝者も必要とはしない。だが、真実な礼拝は喜ばれる。「神へのいけにえは 砕かれた霊。打たれ砕かれた心。神よ あなたはそれを蔑まれません。(詩篇51:17)」
- 主はアラムに対しても、ご自分が真の神であり、真に頼るべき方であることを示すため、ナアマンをツァラアトという病に冒された。一旦ツァラアトに冒されれば、自然治癒はほとんど望めない。それでもナアマンは主君に重んじられていたので軍の長の地位に留まっていた。
- 彼に主が与えたもう一つの恵みは、イスラエルからさらってきた娘によって、サマリアにいる主の預言者の存在を教えられたことだった。彼女は自分を奴隷とした主人に愛情をもって使え、病の回復を心から願っていた。ナアマンはそんな彼女を信頼し、迷信深い小娘のたわごととは思わず、彼女のことばを信じ、その話を主君にも告げた。すると、主君も信じ、イスラエルの王への手紙を書いてくれた。なんと素直で積極的な態度だろうか。対照的にイスラエルの王は陰謀だと思った。
- 彼らが信じた理由の一つは、自分では解決できないことを認めていたこと。心が砕かれていたから、頼るべき方を求めたのだ。このような依存しやすい状態は、誤った教えでも信じてしまいやすいので要注意なのだが、イスラエル王のような、自分しか信じない心では、正しい教えを聞いても頼らない。心が砕かれた時に正しい教えを聞くことができた人は幸い。それは主の導き。
2.
- ナアマンはエリシャの家の入り口に立った。しかし期待に反して、預言者は姿を見せず、使者によって「ヨルダン川で7回身を洗え」と告げられた。侮辱されたと思ったナアマンは怒って帰ろうとするが、僕たちみ「難しいことならきっとなさったのではありませんか?」と忠告されて思い直し、ヨルダン川に下って行った。
- ナアマンが怒った理由は何だったのか?
①期待はずれ。ナアマンは思い描いていた期待とかけ離れていた預言者の対応に怒った。自分で勝手に抱いた期待が外れるのは、仕方のないことであり、怒るのはお門違い。しかし似たようなことは私たちにもあるのではないだろうか。
②ヨルダン川への嫌悪感。ヨルダン川は綺麗な水ではない。綺麗な静水で洗えと言われれば気持ちも違ったかもしれない。しかし水に癒しの力があるわけではないので、問題のすり替え。要は課題の中に嫌な点が含まれていたので毛嫌いしたのだ。真に大切なのは素直に従う謙虚さ。主に対して謙虚になれなければ頼れない。
③簡単すぎる。やっとの思いで来たのに、与えられた課題が簡単過ぎて、信用ができなかった。僕はこの点を指摘し、ナアマンも「難しさ」や「難しい課題にも取り組む自分の偉さ」に依存していた非を認めた。
- ナアマンの良いところは、非を認めるとすぐに切り替えて預言者の指示に従ったこと。自分の間違いを理解しても意地を張っていることはないか?一刻も早く方向を変えないと、ますます時を失う。ナアマンは預言者の言葉通りヨルダン川で7回身を洗い、癒された。途中でやめずに、言われた通りに7回洗ったところが大切。川の水ではなく、主が癒してくださったことがよくわかる。
3.
- ナアマンは喜び、「神の人」の前に立った。今度は預言者は姿を見せていた。顔を合わせて語り合うことが必要な局面だったのだ。ナアマンは感謝の贈り物を捧げようとしたがエリシャは受け取らなかった。なぜ受け取らないのか?26節には「今は金を…受け取る時だろうか?」というエリシャの言葉が記されている。今、受け取るなら、結局はお金という印象が残る。
- 気持ちの納まらないナアマンは、受け取ってくれない預言者ではなく、直接主にいけにえをささげようと考え、その実行のために、イスラエルの土を持ち帰る。実際にはアラムの土の上で捧げても支障はないはずだが、エリシャは彼の気持ちを大切にしてそれを認めた。また、王の礼拝の付き添いをする必要上、偶像の神にひれ伏す形になることの許容を求めたが、それもエリシャは認めた。信仰スタイルはイスラエルに住む者と異なるが、主を信じる点を認め、許容範囲を広げたのだろう。こうして、アラムにも主を信じ主に頼る者が起こされた。
- ここでエリシャに仕えるゲハジという人が面倒を起こす。ナアマンから贈り物を受け取らなかったことに不満を抱き、ナアマンを追いかけ、嘘をついいて金品を受け取った。彼は思惑通りに金品を受け取ることができたが、ナアマンのツァラアトも受け継いでしまった。主より金に頼る者がどうなったのかを覚えておかなくてはいけない。ただし、後に彼は王にエリシャの功績を語る場面が出てくる(8:4)。痛い経験も、別の形で用いられることも覚えておきたい。
結
- 私が頼るべきお方は誰だろうか。
- そのお方に私は本当に頼っているだろうか?
- 私が頼ることを妨げているものはないだろうか?
- ナアマンのように心を整えられ、素直に主に頼ろう。
PAGE TOP