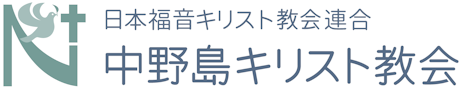2025年5月18日 主日礼拝

序
「逃れの町」は人間が考案して生み出された規定ではない。.
1.神が定めた避難所
- 出21:12-13 人を打って死なせた者は、必ず殺されなければならない。ただし、彼に殺意がなく神が御手によって事を起こされた場合、わたしはあなたに、彼が逃れることができる場所を指定する。
- 民数記35:13-14 あなたがたが与えるべき町は六つの逃れの町で、それらは、あなたがたのためのものである。このヨルダンの川向こうに三つの町を、カナンの地に三つの町を与えて、逃れの町としなければならない。
2.逃れの町の役割
- 事情聴取:門は裁判の場ともなった。長老は町の行政や司法における責任者。事情を聞いて保護すべきか否かを判断した。いつ誰が逃げてくるのかわからないので、いつも急に対応しなければならず、正しく判断するために詳しく事情聴取する必要があった。
- 保護:保護すべきと判断するとその人を受け入れ、場所を与える。いつでも受け入れられるように備えておく必要があった。備えがないと、まともに事情聴取もできなかっただろう。いつでも受け入れられるように待機するのは、非常に大きな犠牲を伴う。
- 保護期間:正当な裁判を受けるか、大祭司が死ぬまで。裁判は訴える側や証言者も同席しないとできない。準備に時間がかかる。大祭司は民の代表として罪を贖う立場。彼の死は恩赦をもたらした。
3.十字架の贖いを表す
- 大祭司の死が恩赦をもたらすのは、キリストの死による贖いを連想させられる。「逃れの町」という規定はキリストによる贖いを示している。
- その町の人々(レビ人)は、具体的な行動で人をかばった。主イエス・キリストも、具体的にご自分をささげ、人となり、人々と親しく交わり、ご自分の体を罪の犠牲とした。神による救いは具体的。
結
- 人の事情を聞き、かばい、とりなして助けるのは、ある特定の人々だけのなすべきことではない。たまたま自分が居合わせたところで問題が起きるなら、自分も「逃れの町」の役割を果たすことになりうる。どうせ助けられないと思ってしまえば、関わりたくないとも思うだろう。
- 神はいつでもかばえるように備えておくことを教えておられる。自分のためだけでなく、いつでも誰かの役に立てるように、何らかの備えをしておくことが望ましい。