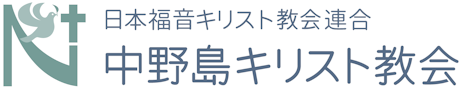2025年5月4日 主日礼拝

序
誰かが困難に立ち向かう姿は感動的。だが、自分自身が困難に直面した時には、困難を避け安易な道を求めてはいないだろうか。困難のもたらす祝福について学ぼう。
1.ヨセフ族の要求
- イスラエルは、カナンの地を自分たちのものとした。しかし、占領は一気に進んだのではなく段階的に進んだ。イスラエル全体による軍事行動で、ある程度の土地を攻略したが、攻略が難しいところは後回しにされたのだ。その段階で各部族にくじで相続地が決められたが、受け継いだ相続地内には未攻略の土地が含まれていた。その攻略は、各部族の責任で行うように求められたのだ。
- 14節でヨセフ族はヨシュアに対して、自分達の相続地が足りないと訴えた。自分達の人数の割に狭いと言うのです。この訴えは正しいのか?ヨセフ族はマナセ族とエフライム族の2つの部族の総称。地図を見るとマナセ族はヨルダン側の東西に広い土地があり、エフライム族も他の部族と比べて狭いとは言えない土地を受け継いでいる。
- ただし立体図を見るとその土地は山地が多く、平らな所は狭い。ヨセフ族はその観点から要求しているのだろう。
2.ヨシュアの答えとヨセフ族の再度の訴え
- ヨシュアは人数が多いのだから、皆で森を切り開いて居住地を広げるように答える。
- しかしヨセフ族は「山地開拓」というヨシュアの提案に「十分ではない」と消極的。その上で、住みやすい平地に住むカナン人は鉄の戦車を持っているので、戦っても勝ち目がないと訴える。要するに、自分達の割り当て地は問難が多すぎるので、もっと住みやすく攻略しやすい土地を与えて欲しいと訴えているのである。
- 困難を強いるのは一種のハラスメント。困難を強いることが非現実的で不当だと感じ、もっと達成しやすい道を求める訴える心理自体は、理解できる。
- 私たちも「善を持って悪に打ち勝ちなさい(ローマ12:21)といった教えは高尚すぎて、達成不可能な理想論だ」などと、ヨセフ族と似た考えをしてはいないだろうか?
- だが、本当にヨセフ族はハラスメントの犠牲者なのだろうか?
3.ヨシュアの積極的な姿勢
- ヨシュアはヨセフ族が数が多く大きな力を持っていると評価する。また、土地が足りないと言う必要性も認める。だからこそ、土地を広げるためにその力を用いるように励ました。
- 困難があることも認めた。「山地」という困難に対しては、切り開いて「隅々まであなたのものとしなさい」と命じた。障害となる難敵については、彼らがいるままでは自分達の土地を広げられないから、彼らを追い払えと命じたのだ。主の助けがあれば困難を乗り越えられると信じて、励ましたのである。
- ヨセフ族は、敵の強さは考えていたが、主の力によってエリコの町を攻略した経験は考慮されていない。今、直面している問題は過去の経験とは別問題であり、主の助けを期待して冒険をするべきではないと思っている。彼らには主への信仰があったのか?彼らに困難が与えられたのは、信仰を働かせるようにという、主の促しだったのではないだろうか。
- ヨセフ族のような不信仰の問題は、私たちにも潜んでいる。聖書を学んで神の偉大さを頭では理解しているのに、自分自身の現実問題にも神の偉大な助けが与えられるとは思えず、できるだけ無難で常識的な方策で乗りこようとしてしまうことはないか。無難で常識的であること自体が悪いのではないが、戦うべき時には無難さが仇となりやすい。サタンは安易な道を示して誘惑する。
- 第二次対戦前の日本のキリスト教会の多くは、礼拝プログラムの冒頭に皇居遥拝や君が代の斉唱を加えていた。それは当時の日本人としては、無難で常識的なあり方だった。模範的な国民である事が神のみこころだと信じ、積極的に政府に協力し、勝利を願い祈り続けたのだ。しかし主への礼拝に偶像崇拝を持ち込んだ罪は大きい。当時の教会の多くは、戦いを避けることで生き延びたが、戦いを避けたので信者の信仰は成長せず、周囲の人々に感銘を与える「あかし」も残せなかった。残ったのは隠れキリシタン的な生き延びる信仰。そこにも意味はあるが、証と言えるのか。信仰のゆえに投獄された一部の指導者たちがいたことは慰めだが、戦後もキリスト教が伸びないのは、困難を乗り越えた良い証が少ないから。困難こそ良い証がなされる機会なのである。
結
ヨセフ族にとっては、ここからが正念場。主を信じて、戦うべき相手に立ち向かうならば、祝福がある。私たちも同じ。困難を感じる時が大切。主を信じて、罪を敵とし、主に従い、主の福音をあかしし伝える戦いに進もう。