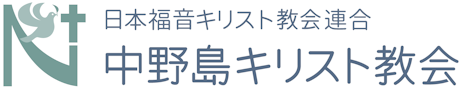2025年6月29日 主日礼拝
1.神々との対比
・イスラエルの先祖アブラハムの父テラは、メソポタミの神々に仕えた。
- またエジプト在住中には、エジプトの神々に囲まれていた。
- 出エジプト後も、イスラエルの中には偶像崇拝が絶えなかった。ヨシュア以後も、主を信じることに熱心な時代と、偶像に仕える時代を繰り返した。
- 現代にもたくさんの偶像があるので、その影響力については察することができる。古代においては、現代以上に偶像は人々に強い影響を与えた。
- 像という物の存在だけが問題なのではない。その偶像の神が人々に人気があったり、この宗教でいいことがあったり逆に粗末にして悪いことがあったといった、人々の声(あかし?)こそが影響力を及ぼす。それは今も全く同じ。
- 偶像の神々に翻弄された過去を持つ自分たちを、主は導き、エジプトから解放し、今住む地を与えてくださったと、ヨシュアは振り返り、確認した。
2.主の偉大さ
- 誰に仕えるのかというヨシュアの問いかけに、イスラエルの民は、主を捨てて他の神々に仕えるなどあり得ないと答えた。
- 民も、エジプトからの解放と、カナンの地の平定は主によると認めていた。主によるという事実の受け止め方で一致できたのは幸い。
- ヨシュアは厳しく問い直したが、民は再度誓った。
- 水の上を歩き、風を恐れて沈んだペテロを思い起こす。主に心を向けている時には、信じ従うことは当然のことと思える。しかし心が主から離れると、とたんに不信に陥ってしまう。
- この時のイスラエルは主に心を向けていた。ヨシュアは彼ら自身が証人だと言い、信仰が一時の気まぐれで終わらないように、誓わせた。
3.誰に仕える
- 仕えるとは、主人としもべの関係を想定している。
- 私たちは自立的存在ではない。必ず何かに依存している。依存の必要性を自覚し、依存する相手に相応しい態度を取ることが「仕える」ということ。自分の弱さ、はかなさを自覚していないと、仕える気持ちにはなれない。
- 誰に仕えるのかが問題。謙虚に自身の弱さを自覚し、素直に頼る良い姿勢を持っていたとしても、仕える相手を誤えば、大変なことになる。
- 日本人のルーツを探ると、神道的な神観を伝統的に持ってきた。それで、日本人の気質は多神教向きであり、キリスト教にはなじみにくいと考える人もいる。頷ける面もあるが、一面的な分析である。。
- もっとルーツを辿り、ノアにまで行きつけば、私たちの先祖は主を信じていた。さらにアダムまで遡れば、主とともに暮らしていた。造り主に仕えることが、人間全てにとって、最も自然である。主に仕えることを選び取ろう。